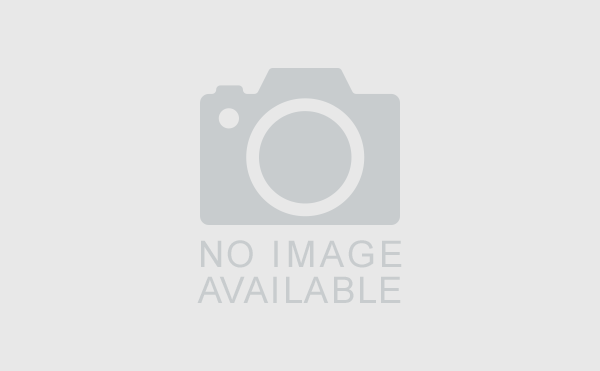栄養機能食品で検討スタート 栄養成分の機能表示見直しへ 上下限値も一部改正
消費者庁は10月8日、「栄養機能食品に関する検討会」(座長:東京大学名誉教授、佐々木敏氏)の初会合を開催、栄養機能食品の表示や基準値の見直し議論を開始した。検討会を経て、2026年度末までに「食品表示基準」の一部改正を行う予定。
栄養機能食品制度は2001年4月に創設。栄養成分の機能を表示できる対象はビタミン13成分、ミネラル6成分、脂肪酸1成分の計20成分となっている。これまで、成分の追加や下限値・上限値の見直しは行われてきたが、栄養成分の機能表示、摂取上の注意事項の文言は見直しが行われてこなかった。特に機能表示に関しては、食事摂取基準の前身である「栄養所要量」2000年版に基づいており、現行の食事摂取基準に記載されたエビデンスとの乖離が生じいていた。

こうした状況を踏まえ、必要な見直しを議論する検討会を発足。今年度は3回程度開催し、「下限値・上限値」「栄養成分の機能」の規定について議論する。来年度は「摂取をする上での注意事項」について検討を行う。
初会合では消費者庁が、「下限値・上限値」の改正案を提示。下限値は、これまでと同様、栄養表示の基準となる「栄養素等表示基準値」の30%で算出した。数値が変わるのは、亜鉛、カルシウム、鉄、銅、パントテン酸、ビタミンB1・B12・D・Eの9成分。ビタミンDの場合、現行の1.65㎍から2.70㎍に引き上げる。
上限値については、亜鉛を15㎎から17㎎、銅を6.0㎎から4.6㎎、マグネシウムを300㎎から320㎎に改正する案を示した。
栄養成分の機能表示に関しては、21年度と23年度に実施した調査事業を踏まえて、改正案を作成した。ビタミンCの場合、現行制度では「皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です」となっているが、「ビタミンCは、抗酸化作用により、細胞を酸化障害から保護するのを助ける栄養素のひとつです」「ビタミンCは、皮膚や粘膜、骨、血管のコラーゲン合成を助ける栄養素です」「ビタミンCは、腸管での鉄の吸収を助ける栄養素です」に改正する案を示した。表示については文末表現の整理を含めて、引き続き次回会合で議論する。